パイオニアの原点 | 森岡東洋志氏
テクニカルディレクターたちの未来を開く

「社会や未来のために活動する人びと」に焦点を当て、活動の原点を探る企画「パイオニアの原点」――第6回は、2020年に一般社団法人テクニカルディレクターズアソシエーション(TDA)を立ち上げた森岡東洋志氏にインタビューし、活動を通じて目指したい社会像に迫りました。
聞き手:川村 健一、中川 真由美、小泉 朋久
テクニカルディレクションをビジネスとして確立する
――森岡さんはテクニカルディレクターとして第一線で活躍される中、テクニカルディレクションが優れているプロジェクトを表彰するアワード「テクニカルディレクションアワード(Tech Direction Awards)」を2023年に新たに設立されましたが、なぜこのような活動をしようと思ったのでしょうか?
僕が所属しているBASSDRUM(ベースドラム)は広告業界においては世界初のテクニカルディレクターを中心とした組織です。テクニカルディレクターのプレゼンスや価値を高めていくことを目的として掲げ、2018年2月に設立しました。ギターやボーカルではなくベースとドラム。クリエイティブやビジネスのバックボーンを支えるリズムセクションとして「技術」を必要とするものすべてをカバーすることを目指し活動しています。
テクニカルディレクションとはどんな仕事かというと、あるクリエイティブアイデアがあったとして「この技術でつくれそう」「今のままでは実現が難しい」「こうすれば設計できる」――このような「クリエイティブ」と「技術」を媒介する役割を担っています。技術者であれば当たり前におこなっていることですが、つくる部分とは異なるタスクです。当初はBASSDRUMとしてテクニカルディレクター向けのワークショップや勉強会をおこなっていたのですが、さらに活動を広げていくために立ち上げたのがTDAです。

最初の2年間は会員数200人ぐらいでコミュニティ活動を中心におこなってきました。テクニカルディレクター同士のコミュニケーション環境は整ってきたため、より多くの人びとへ認知を広げる方法を検討し、具体的なプロジェクトを通じてテクニカルディレクターの価値を知ってもらうべくテクニカルディレクションアワードを設立しました。
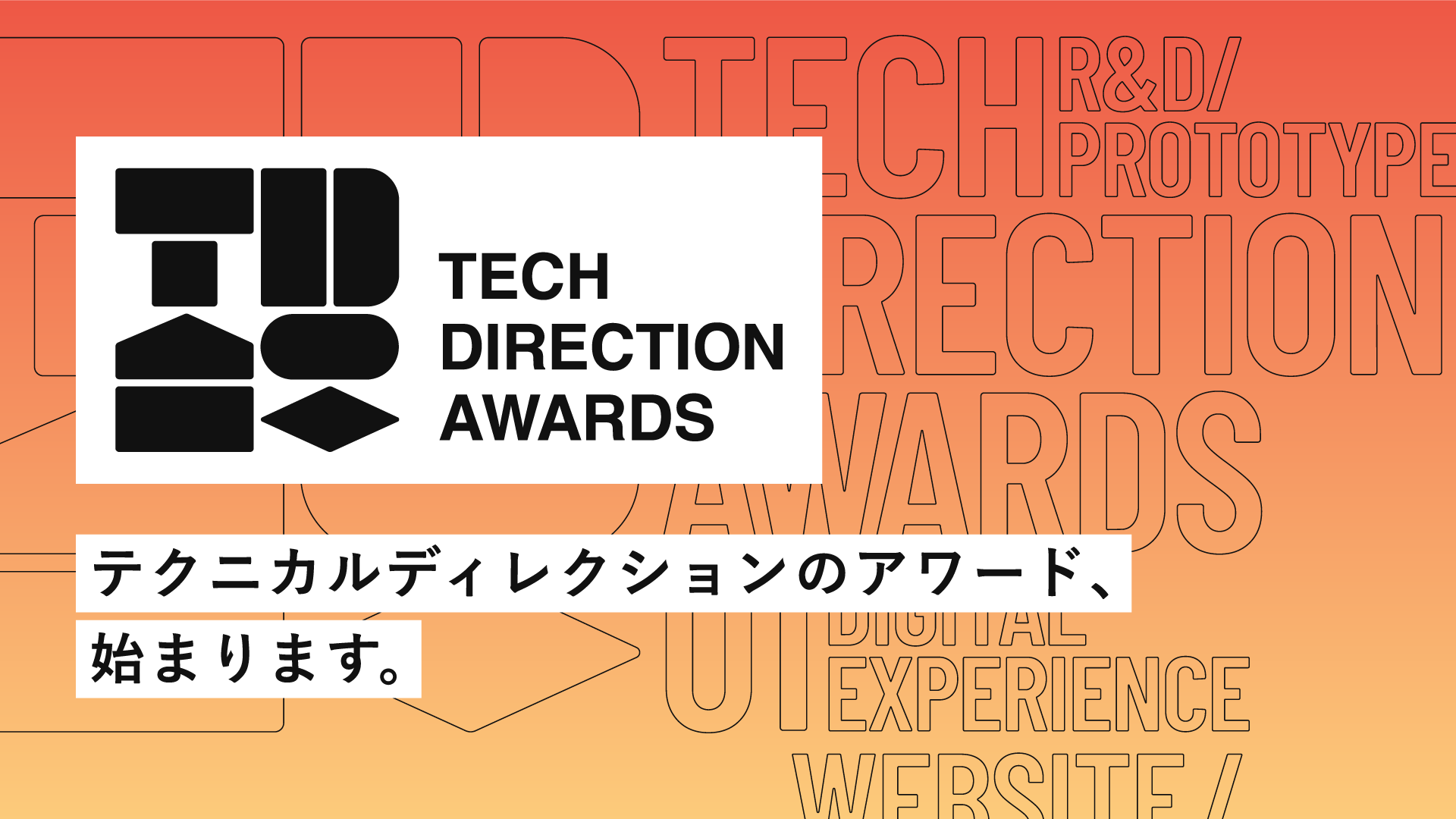
――かつて技術のフィジビリティは受注前におこなうケースが散見されていましたよね。
自分たちのところに仕事が来れば制作費として回収できますから無料のサービスでも成り立っていたのですよね。ただ、フィジビリティを突き詰めると「その企画はやらないほうがいいですよ」という話をしなければいけないときもあります。ビジネスとして責任をもつにはテクニカルディレクション単品でマネタイズできる環境をつくる必要がありました。
――そこでTDAのような活動を通じて、テクニカルディレクションの価値を啓発しているわけですね。
広告業界の中では新しい職能なので、多くの人びとにテクニカルディレクションの価値を知っていただくことが必要でした。みんながその価値を認識できるようになると、スコープや予算が制作費とは別になり、テクニカルディレクション自体の責任を全うできるようになるわけです。実際、BASSDRUMでは広告事業を主としないクライアント側に加わり「実現性を担保する」「仕様をつくって提供する」「経営者や開発パートナーと並走する」といった仕事が多くなっています。
――テクニカルディレクションの価値が浸透してきた理由には、どのような背景があると思いますか?
ビジネスにテクノロジーがなくてはならない時代になったという点が大きいと思います。僕の仕事でいうと、広告施策としてIoTデバイスのプロトタイプをつくり、反響をみて事業化しようといった相談をよくいただきます。クライアント側に事業としての可能性があるということを理解いただけるようになったということかと思います。
そうした背景もあり、テクニカルディレクターの仕事は業界を超えた広がりを見せています。広告業界でテクニカルディレクターとして活動されていた方が別の業界でサービスやプロダクト開発に関わっているケースが増えていて、実際、テクニカルディレクションアワードでもそのような事例の応募を多数いただいています。
テクニカルディレクターの価値と役割
――自社でプロダクトを開発している事業会社から見て、テクニカルディレクターにはどのような価値があるのでしょうか?
事業会社で新しい製品を考えるときのチームは、企画部のプランナーさんやデザイナーさんが多いのですが、一緒に動いてくれる技術者は意外と少ないようです。技術者のキャリアプランとしてそういう道がない状況なのかと思います。
広告業界のテクニカルディレクターや技術者は「UXから逆引きするモノづくりに慣れている」という特徴があります。「ウェブサイトなら、あのAPIが使える」「アプリのSDKを使えば実現できる」「オフラインイベントならあのセンサーが使える」――このように技術をUXに最適化することに慣れているわけです。企画段階では関係者がいち早くUXを体験することが重要ですが、企画時のプロトタイプをつくるのと、オフラインイベントで3日間動いていいものをつくるのはスキルとしては非常に近く、そういう感覚でモノづくりができることって実はすごい強みなのです。
――あらゆる場面で技術の重要性が語られている一方、テクニカルディレクターや技術者は想像以上に少ない印象があります。
それはそうだと思います。僕の前職は社員150人ほどの会社で技術者が20人程度、テクニカルディレクターが5人。技術者4、5人に対してテクニカルディレクターが1人つくようなチーム構成でした。これでも十分ではない状況ですよね。しかし、多くの会社ではもっとテクニカルディレクターが少なく、組織内だけではスキルやノウハウがたまらないため、組織を超えて横のつながりをつくる必要があるのですよね。
――少数だからこそ連携の重要性が本能的に身についている業界であるということですね。

――テクニカルディレクターは「つくる部分を担う技術者とは異なるタスク」というお話がありましたが、同じ方がそのタスクをおこなうとどのような弊害があるのでしょうか?
テクニカルディレクターは仕様書を書いたり、見積もりをつくったり、クライアントとの対話力が問われる一方、技術者はつくることの実力が問われます。世の中にはとても優秀なスーパープログラマーみたいな人がいます。そういう方にテクニカルディレクションもお願いしてしまうと、技術者としての稼働時間が減ってしまい生産性が下がるわけです。技術者とテクニカルディレクターとで分業ができれば、お互いの強みが足し算ではなく掛け算になるのですよね。
他分野から学ぶ
――テクニカルディレクターの環境はかなりよくなってきたと思いますが、今、課題に思っていることはありますか?
テクニカルディレクターの認知度をさらに上げるにはどうすればよいのかという点です。その意味でいうと、他分野の成功事例を参考にしています。例えばデザインの分野はわかりやすいですよね。経営者とクリエイティブディレクターが並走しているようなケースが多いように、テクニカルディレクターもそうなったほうがいい。頼まれたものをつくっているだけでは結果にコミットしていると言えないですから。
デザイン思考という言葉が確立されているように、デザインは高度に抽象化されメソッド化も進んでいます。テクノロジーにはテクニカル思考みたいな概念がない。技術との向き合い方・体系化みたいなことをどう実現していくのかというのは大きな課題です。
――デザインの分野との対比というのは非常に面白いですね。考え方として両者にはどのような違いがあると思いますか?
デザインは最終成果物に価値がおかれます。手書きだろうが、3DCGだろうが、5分でつくろうが、5日間かけてつくろうが、成果物に人を動かす力があれば成立します。一方、テクノロジーはよい絵が出ても10回に9回エラーで落ちるようではシステムとして納品できないように、どうやってつくっているかがすごく大事なのです。見た目以上に「プロセスのノウハウに価値がおかれている」といえると思います。
目指す世界
――BASSDRUMでは子どもたちを招いてテクノロジーのワークショップをおこなっています。ビジネスからやや遠い文脈ですが、なぜ実施されているのでしょうか?
日本には子どもがテクノロジーに触れる場ってあまりない気がしています。「テクノロジーって楽しい」という自分ごと化ができるとテクノロジーの理解が一気に進みますから、こういう場こそテクノロジーの普及に必要だと思っています。必ずしも全員がテクニカルディレクターや技術者にならなくてもよく、テクノロジーとの向き合い方がわかっている方が増えれば増えるほど、テクノロジーの価値が認知されていく。草の根でもいいからできることをやってみようという感覚で取り組んでいます。
――お互いを知ることからリスペクトが生まれるように、テクノロジーとの向き合い方がわかっている人とのビジネスは圧倒的に仕事がスムーズに進みますよね。
お互いをリスペクトし合えない状態は仕事として不健全ですよね。BASSDRUMはクライアントのゼロイチを手伝うことが多いのですが、イチができた頃にはクライアントの中でCTO候補が立っていてその方にバトンタッチしていくという流れが組めるのが一番理想だと思っています。重要なのは「技術への向き合い方を知っていただくこと」であって、すべてを外注にしていたら人件費が膨らみ、もうかる事業ももうからなくなりますし、内部から技術を活用した新しいアイデアが生まれなくなってしまいます。僕らは早く抜けたほうがよくて、クライアントが自走できる状況をつくることこそ、仕事だと思っています。クライアントの事業をバックボーンから支え、テクニカルディレクターという価値を普及させていった結果、自分たちのバリューが上がり仕事もしやすくなる、そんな世界を願って活動しています。
――最後に、未来のパイオニアに対して一言お願いします。
何より大事なのは、夢中になれることを見つけることだと思います。「これは好き」「これは嫌い」――二択でいいので自分の傾向を自覚してみることから始めてみると効果的です。例えばピンタレストで自分の好きなビジュアルを500作品ぐらい集めてみると自分の好きな傾向がわかってきます。それで終わらせず、なぜ好きなのか常に意識し言葉にする癖をつけると自然とメタ認知が磨かれていきます。
テクノロジーでよく陥るわなともいえますが、メジャーなツールに表現が引っ張られるところがあると思います。大事なのはツールのノウハウではなく「新しいものの学び方」「実現したいことを形にした経験」「その制作物で何を実現できたのか」にあります。そういう視点で取り組んでみるとトレンドに流されず自分自身の活動につながるのではないでしょうか。
最後になりますが、いきなり成功を目指さないでください。仕事でも失敗したくないという方がたくさんいます。そんなときによく言うのは「早く・安く・小さく・失敗する数を増やしましょう」ということです。例えばプロトタイプの予算が1,000万円あったとして、1,000万円で1回つくるよりも100万円で10回つくると成功確率が上がります。気軽に失敗するよう心がけてみてください。チャンスの数を多くつくることが成功への近道です。
インタビューを通して
「孤独な者よ、君は創造者の道を行く。」――19世紀・ドイツの哲学者、フリードリヒ・ニーチェの言葉だ。森岡氏が創造をつづける背景には新たな環境に挑みつづける多くの選択があった。孤独に閉じることなく他者に誠実で相互に高め合えるからこそ、周囲に人が集い、熱量のある場が生まれるのだろう。森岡氏の歩みから、どのようなリズムが生まれていくのか、これからの活動に注目したい。
Text by Ken-ichi Kawamura
Photographs by Hirokazu Shirato

森岡東洋志 もりおか・とよし 一般社団法人テクニカルディレクターズアソシエーション代表理事
ベースドラム株式会社 Tech Director1981年生まれ。東京工芸大学博士課程満期退学。工学修士。メーカー勤務を経て、2014年からワントゥーテンデザインにてIoTデバイスの開発やスマートフォンアプリのSDK開発、インスタレーションの開発に携わる。2015年、プロトタイピングに特化したワントゥーテンドライブを設立し、CTOとしてメーカーとの新製品開発やテクノロジーを使ったエンターテインメントの開発を行う。2018年、本体ワントゥーテンのチーフマネージャーに。2020年に独立し、BASSDRUMに参画。大阪芸術大学にて非常勤講師も務める。
