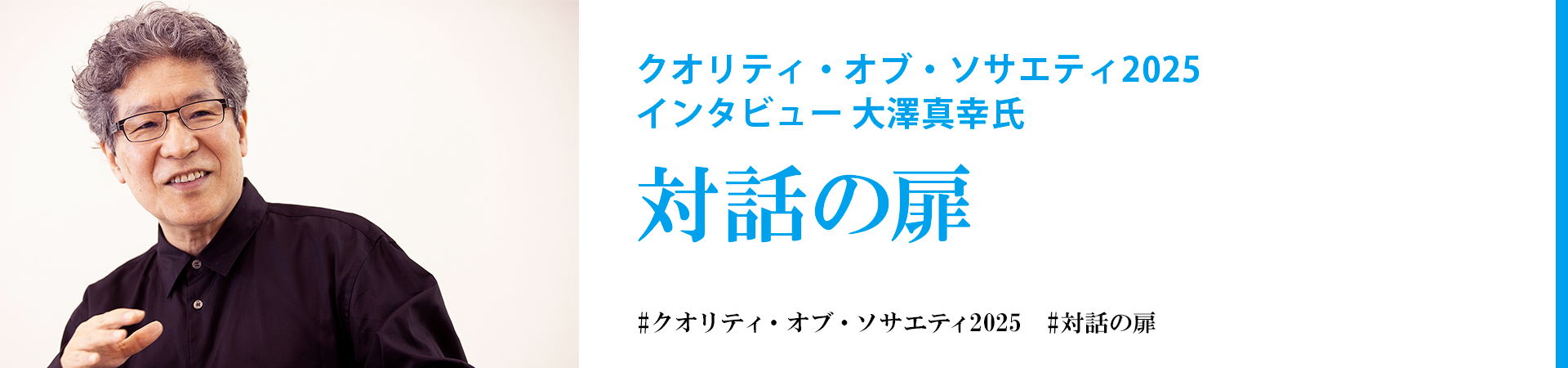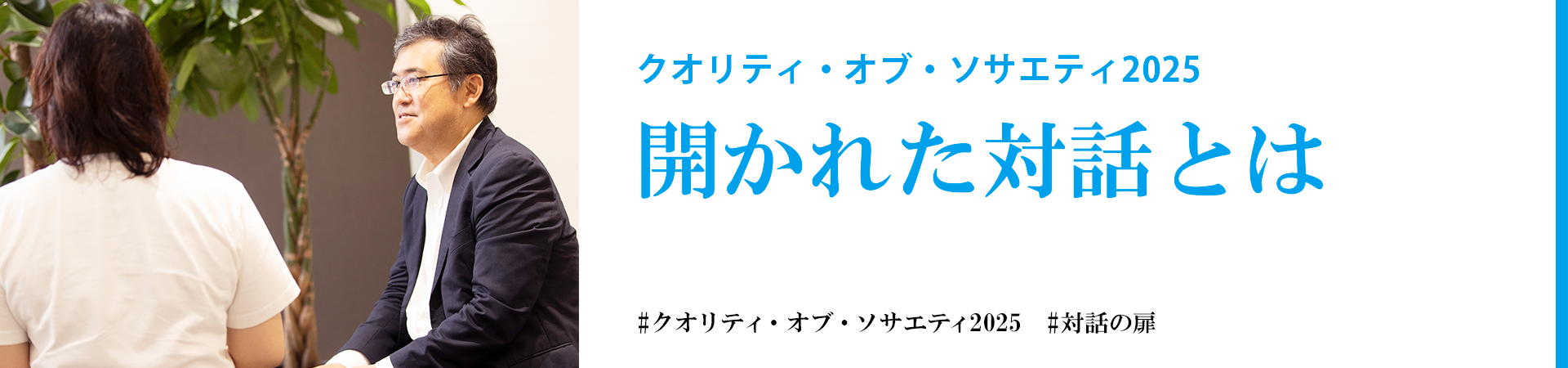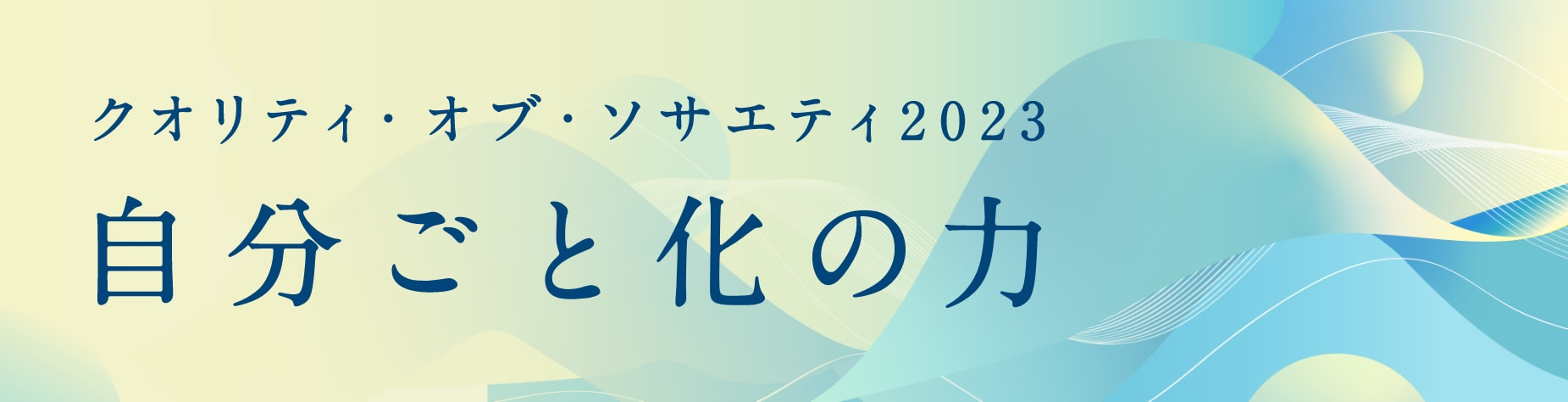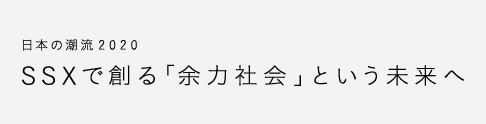クオリティ・オブ・ソサエティ2025
今、考えたい「対話」のキーワード

私たちは生きていく中で、対話を通して何かを受け止め、整理し、応答し、別の何かを発見します。その対話の相手は、他者や社会、また自分自身かもしれません。これからの社会を生きていくための手掛かりとして、対話に関連する六つの視点をキーワードとして取りまとめました。
○機微
――容易には察せられない微妙な事情・おもむき(広辞苑)。
言葉によるコミュニケーションだけでなく、相手の表情やしぐさから気持ちを推しはかり、理解しあうことを大切にする文化が日本にはあります。例えば、伝統芸能の「能」は、象徴的な動作と洗練された表現で知られており、能面を使った表現は、頭のわずかな角度や演者の動き、また観客側からの心情の投影などによって、その表情に微妙な変化が生まれ、言葉を使わずに感情や物語を伝えています。パナソニック創業者の松下幸之助は、「人情の機微は教えることができない。学ぶのではなく、自分で悟るしかない。人情の機微こそが人生の根底である※1」と述べています。
近年、多くの企業で「1on1ミーティング」や「対話会」が導入され、「傾聴」がクローズアップされています。傾聴は、会話を重ねる中で、話しづらいことも言葉として顕在化させて「聴く」ことだとされています。うなずき、相づち、アイコンタクトなどの非言語コミュニケーションや共感も重要なポイントとなります。デジタル技術の進展により、遠隔でも、AIやロボットでも、非言語情報を含めた相手の機微を推測することは可能になると考えられます。心の機微に触れて他者との関係性を配慮することに改めて注目したいと思います。
-
※1出典:『リーダーになる人に知っておいてほしいこと』松下幸之助(述)、松下政経塾(編)、2009年

○間(ま)
――物と物、ある事とある事など、同質なものの隔たり。
「間(ま)」には、①物的空間、②時間的空間、③心理的空間※2があります。障子や襖を用いた物的空間としての「間」づくりは、空間を完全に隔てず、隣の部屋や外界とをつなげるものです。そこで感じられる気配を重んじることで家族や空間を共有する人の間に礼節が生まれ、互いの気持ちを察する心が育まれてきました。また、時間的空間の「間」は阿吽の呼吸を生み出し、以心伝心、コミュニケーションにおける相互信頼につながっています。
現代では、対話型AI市場が拡大の一途をたどっています。大規模言語モデル(LLM)による対話型AIは、会話の抑揚や「間」を調整することで人間の話者と変わらないテンポを実現し、会話における違和感を無くしつつあります。対話型AIは心地よいと感じる心理的な「間」を活用することで、人間から親近感や信頼感をもたれるようになり、気軽な相談相手としての役割も担うようになることが容易に想像されます。しかし、AIがその「間」の意味を本当に理解しているかについては別の問題として議論が必要です。
-
※2①物的空間、②時間的空間、③心理的空間:「間(ま)を空ける」とした場合、①物的空間では「距離を置く」、②時間的空間では「少し待つ」、③心理的空間では「関係を疎遠にする」という意味がある

○内省
――自己の心的過程を自ら観察すること(岩波 哲学・思想事典)。
「内省」は3000年以上前のギリシャで既に、哲学の概念として存在していました。かつてデルフォイのアポロン神殿には「汝自身を知れ」という格言が掲げられており、ソクラテス※3の言葉であるという説があります。古代ローマ帝国の全盛期を支えた、皇帝マルクス・アウレリウス※4は、日々の思索や内省の言葉を『自省録』として残しています。日本文化の精神性も極めて内省的です。古来日本は、大陸から文化を取り入れ、その文化を昇華し、自らをさらに深く掘り下げることで「わび・さび」の文化を形成しました。
内省を実践する手段の一つに「日記」があります。昨今は、写真や入場チケットを貼るなどしてその日に感じたことを自由にまとめる手書きスタイルの日記も人気で、まとめる行為や、過去にまとめたものを見直すことで、自分自身を客観的に観察することができます。対話を通して相手に自分の意見の背景を理解してもらうために、まず自分自身との対話により、自己の考えを客観的に見るための内省に取り組むことも大切な一歩です。
-
※3ソクラテス(Sōkratēs、前470頃-前399年):古代ギリシャの哲学者。本人による著述は残されておらず、死後に弟子により記された著作からソクラテスの思想や言葉を知ることはできるが、「汝自身を知れ」がソクラテスの言葉であるかどうかの真偽は不明 ※4 マルクス・アウレリウス・アントニヌス(Marcus Aurelius Antoninus、121-180年):第16代ローマ皇帝であり、五賢帝の一人
-
※4マルクス・アウレリウス・アントニヌス(Marcus Aurelius Antoninus、121-180年):第16代ローマ皇帝であり、五賢帝の一人

○仮託
――他の物事を借りて言い表すこと。事寄せること(デジタル大辞泉)。
日本最古の歌集『万葉集』には、亡き貴人に後代の歌人が仮託してつくった歌、女性に仮託する形の歌が見られます。また、土佐国から平安京に帰るまでの55日間を女性に仮託する形でつづった、紀貫之の『土佐日記』の冒頭「をとこ(男)もすなる日記といふものを をむな(女)もしてみむとてするなり」は有名です。このように、日本では古来自分でないものに仮託して自分の気持ちを表現してきました。
『万葉集』や『土佐日記』から1000年以上が経った現代では、何らかの特徴的な人格になりきる行為(例えば、アニメーションなど原作のあるキャラクターのコスプレ、アカウントごとに異なる自分のキャラクター設定、仮想世界のアバター)が身近な仮託であり、今ではコスプレは日本文化を代表するものとして世界中に多くの愛好家がいます。自己表現の一つとしての仮託は、自分のさまざまな側面を見つける“自分自身との対話”でもあり、同時に、あるキャラクターを被ることで言いにくいことを伝えたり、会話が苦手でなくなったりと、“他者との対話”を進める手段でもあります。

○無私
――私的な感情にとらわれたり、利害の計算をしたりしないこと。私心がないこと。また、そのさま(デジタル大辞泉)。
中国の戦国時代について書かれた『戦国策※5』に、「法令至り行われ、公平無私なり」という一節があることからも、「無私」は中国に由来する言葉だと考えられます。日本においては、武士道や儒教における主従関係の心がけとして用いられ、武士だけでなく庶民にも一種の大衆道徳として広まっていったといわれています。『無私の精神』を記した小林秀雄※6はその中で「実行家として成功する人は、自己を押し通す人、強く自己を主張する人と見られがちだが、実は、反対に、彼には一種の無私がある」と述べています。周りの人の意見に耳を傾け、客観的に物事を受け止めるほうが正しい判断と行動ができると考えていました。また、日本では「無」の概念が思想の核になっている※7ともいわれています。「無」は存在(有)を否定しているのではなく、有も無も超えてしまったものとして、さまざまな存在を受け入れることができると考えられています。
現代は「自己実現」「エゴサーチ」といった言葉にも見られるように、個人としてどう成功するか、他者から自分がどのように見られているかなど、「私」を強く意識することが許容される風潮もありますが、これは自律を促す半面、対話よりも自己主張を優先させることにつながりかねないと懸念されます。そんな時代だからこそ、多様な価値観を受け入れて対話を重ね、コミュニティや社会のために何かしようという無私の姿勢が、よりよき未来を開くのではないでしょうか。
-
※5『戦国策』:前漢の学者・政治家であった劉向(前79-前8年)により編集された国策、献策、逸話などをまとめた書。「春秋戦国時代」の由来ともなっている
-
※6小林秀雄(1902-1983年):文芸批評家、編集者、作家
-
※7日本では「無」の概念が思想の核になっている:哲学者の西田幾多郎(1870-1945年)の思想(西田哲学)では「無の場所」「絶対無」「無の自覚」など「無」がキーワードになっており、自らを掘り下げると「無」へと行き着くという観念がある(参考文献:『西田幾多郎 無私の思想と日本人』、佐伯啓思(著)、2014年)

○ハレ
――「ハレとケ」とは、民俗学者の柳田國男※8によって見いだされた、日本人の伝統的な世界観の一つ。「ハレ」は非日常の、特別な日。
漢字で書く場合、ハレには「晴」、ケには「褻」の字が当てられます。稲作を基礎とする日本人の生活にはかつてハレとケの二つの時期があり、両者ははっきりと区別されていました。「ハレ」とは、神社の祭礼や寺院の法会、正月・節句・お盆といった年中行事、初宮参り・七五三・冠婚葬祭といった人生儀礼など、非日常的な行事がおこなわれる時間や空間を指しています。その一方で、ハレ以外の日常生活は「ケ」であるとして、このハレとケとの循環リズムから日本の生活文化が説明できましたが、近代化とともにハレとケの区別があいまいになってきたことも柳田國男は指摘していました。
現代では日常(ケ)を大切にする価値観が広まり、ハレのケ化(飲酒の日常化やファッション文化の普及など)、また、人口減少や核家族化に伴う冠婚葬祭の機会減少と規模縮小も影響して、非日常(ハレ)の場面は少なくなりました。さらにコロナ禍により、多くのイベントや交流に中止・自粛を求められたことも、少なからず尾を引いているように思います。ハレの場は血縁・地縁を通じたコミュニティでの交流機会という役割も、普段からためこんだストレスを祭りなどで発散して社会を維持する装置となる役割も担ってきました。生活の中に非日常(ハレ)が挟まれることは、社会や人びとの生活にリズムと健全さをもたらす機能があると考えられます。コロナ禍を経て、さまざまなイベントや地域の祭りが復活してきています。また、家庭や職場とは異なる非日常空間での対話をおこなう交流会や企業研修へのニーズも生まれています。非日常=「ハレ」の場がコミュニティにおける私たちの対話にもたらす効果に注目したいと思います。
-
※8柳田國男(1875-1962年):日本民俗学を開拓した民俗学者。著書に『遠野物語』(1910年)など

――最後に
ここに挙げた六つのキーワードが対話のすべてではありません。今、この時代に改めて「対話」について考えたり、行動したりするにあたっての一助となることを願ってまとめました。複雑化する社会、発展する技術、分断される人びとの思いをどのように受け止めて、この先の未来につないでいくか、「対話」のもつ可能性を信じたいと思います。