グローバルな解析自動化プラットフォーム構築で成長市場の自動車開発を加速
- ものづくり
- データ分析・活用
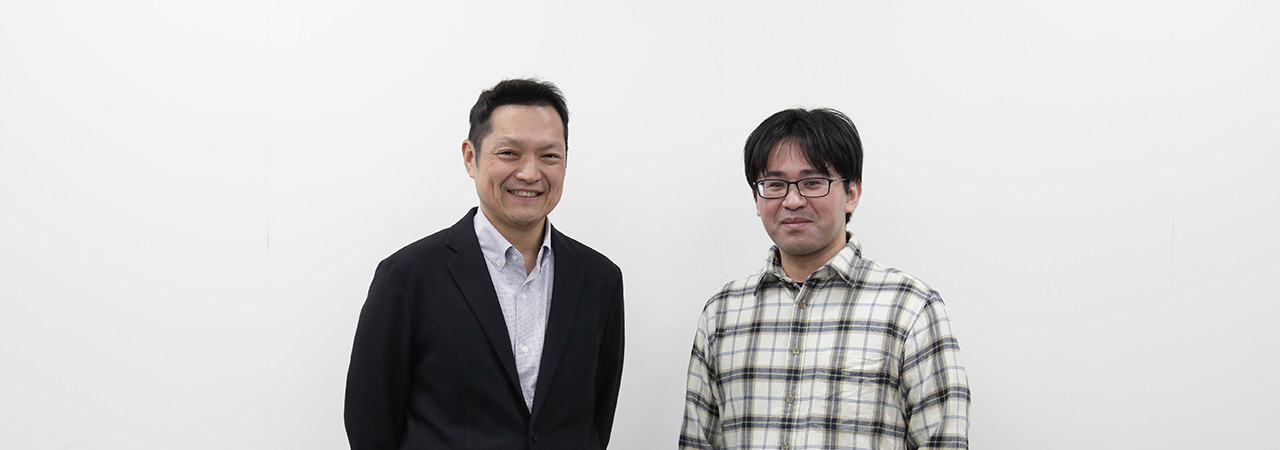 写真左より、スズキ株式会社 IT本部 デジタルエンジニアリング部 CAE推進課 課長 志村明久氏、同課 リードコーディネーター 小鮒慎吾氏
写真左より、スズキ株式会社 IT本部 デジタルエンジニアリング部 CAE推進課 課長 志村明久氏、同課 リードコーディネーター 小鮒慎吾氏1909年創業、軽自動車や小型車に圧倒的な競争力を誇るスズキ株式会社。とくにインド市場ではインド政府との合弁会社 Maruti Suzuki India Limitedを通じ、同国の乗用車でトップシェアを獲得しています。電動化やコネクテッド技術にも力を入れ、環境性能と使いやすさを併せ持つ自動車づくりを推進。2024年3月期の四輪の販売台数は316万台、連結での売上高は5兆3,743億円。堅実な経営基盤のもと次世代モビリティ市場でも存在感を示しています。
同社は早くから設計者向けの解析自動化の仕組みづくりに取り組んでおり、2008年、パワートレイン開発での性能評価や設計最適化を手軽に行える環境を構築しました。2024年、既存のシステムのサポート終了を機に、同社IT本部 デジタルエンジニアリング部 CAE推進課はアマゾン・ウェブ・サービス(AWS)上に電通総研のi-SPiDM(アイ・エスピーディーエム)を展開。成長市場であるインドの現地部隊と日本の設計部隊をつなぐ解析自動化の仕組みを構築しました。
このプロジェクトを指揮した志村明久氏は支援にあたった電通総研のチームについて「明確にあるべき道筋を示し、3ヶ月という短期間でプロジェクトを完遂してくれたことを心から感謝しています。まさに100点満点の支援でした」と話しています。
システム刷新とクラウド移行の同時進行を決断
「プロジェクトの直前まで迷っていました」と話すのはスズキ株式会社デジタルエンジニアリング部で自動車開発のCAEツール導入や環境構築を指揮する志村氏。迷っていたというのは新たな解析自動化環境をオンプレミスで立ち上げるか、それともクラウドに移行させるかです。
もともと同社は2008年よりパワートレイン開発に携わる設計者向けに定常流解析やエンジン性能解析など手間のかかるシミュレーションを自動化するCAEプラットフォームを立ち上げ、15年にわたり運用してきました。しかし、2023年、そのシステムのサポートの終了が決まり、速やかな刷新を迫られていたのです。
「2008年に導入した旧システムは確実に現場に根付いていました」と話す志村氏。「これを新たな仕組みへと置き換えるだけでも大仕事ですが、それをクラウドにもっていくとなるとさらに変化点が増え、問題が生じた場合、原因を特定しづらくなってしまう。それで迷っていました」。
現地部隊との共通基盤、3ヶ月でスピード構築
しかし、最終的に志村氏の決断はクラウドに傾きます。「インドとのコラボレーションを考えればそれが最良の選択でした」と志村氏は説明します。
1982年にインド政府との合弁会社Maruti Suzuki India Limitedを立ち上げたスズキは同国の自動車市場で実績を重ねトップシェアを獲得するまでに成長しています。この強固なポジションはスズキの事業戦略に大きな意味を持ち、現地部隊との共通CAEプラットフォームを築いておくことはその方向性を後押しする決断といえました。「しかし、期限は3ヶ月」と志村氏は振り返ります。「それを達成するには力のあるサポートが必要でした」。
そこで2024年4月、志村氏は電通総研に支援を打診します。もともと電通総研とスズキとは2008年の旧システム構築からつきあいがあり、その堅実なサポート姿勢には信頼を寄せていたと志村氏は話します。「電通総研からの提案やアドバイスは的確で具体性があります」と志村氏は続けます。「今回のプロジェクトは日本サイドだけでなくインドの現地部隊との調整も必須。伝えるべき情報に少しでも曖昧な部分があればプロジェクトが暗礁に乗り上げてしまう危険性もあった」。実際、このプロジェクトはUIの英語化をはじめ、海外データセンターでのインフラ構築など通常以上の調整を要し、綿密な計画と明確なリーダーシップが求められていました。
志村氏とともにスズキのCAE推進グループでクラウド環境づくりに取り組んできた小鮒慎吾氏も電通総研のサポートチームについて「CAEとクラウドという二つの異なる専門領域の知見に長けたスタッフで構成されていて安心できた」と話します。「おかげでプロジェクトは支障なく円滑に進みました」。
試作品質の向上に貢献
このシステムを使えばCAEに慣れていないエンジニアも解析を行えるようになります
スズキ株式会社 IT本部 デジタルエンジニアリング部 CAE推進課 リードコーディネーター 小鮒慎吾氏

2024年6月、プロジェクトは始動し、計画通り9月に完了します。プラットフォームとして選ばれたのは電通総研のi-SPiDM。構造解析、流体解析をはじめとした設計現場で行われる多様なシミュレーションの効率的な実行とデータ管理を両立するWebベースのSPDM(Simulation Process and Data Management)システムです。
ワークフロー標準化や解析結果の共有・コラボレーションにも効果を発揮し、更にトレーサビリティの向上にも貢献します。また、AIを活用したデータ分析やサロゲートモデルの構築、プロジェクト管理ツールとの連携といった特長も備えています。
「この仕組みを使えばCAEに慣れていないエンジニアも解析を行えるようになる」と小鮒氏はそのメリットを語ります。「いま大変革のなかにある自動車業界。今後、電動化が進むにつれ求められる解析技術も変わっていくでしょう。そうした変化にもこのプラットフォームなら対応できます。誰でも使えるので設計の工数削減に力を発揮します」。
良いものを、より速く、低コストで
電通総研のサポートには心から感謝しています。まさに100点満点の支援でした
スズキ株式会社 IT本部 デジタルエンジニアリング部 CAE推進課 課長 志村明久氏

スズキでは現在、数百名のエンジニアがこの仕組みを活用してエンジンの定常流解析や性能最適化などを行っており「初回の試作のレベル向上に貢献できている」と志村氏は話します。今後、インド現地チームの規模が拡大するにつれi-SPiDMはさらに大きな成果を生んでいくだろうと志村氏は予測しています。
「電通総研のサポートには心から感謝しています」と話す志村氏。「時代の流れによって開発する製品やものづくりの方法は変わっていきます。しかし、良いものを、より速く、より低コストで作っていくことに変わりはありません。そこには必ずシミュレーションのニーズがある。設計者たちは多忙なのでいかに手間をかけず求める諸元を探り出せるか、仕組みづくりを通じ今後もそのニーズに応えていきます」。
-
※記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
-
※記載情報は取材時(2024年12月)におけるものであり、閲覧される時点で変更されている可能性があります。予めご了承ください。




