なぜ今、新しいL1チェーンなのか
~ステーブルコイン時代におけるWeb3技術の交点〜
なぜ今、新しいL1チェーンなのか
~ステーブルコイン時代におけるWeb3技術の交点〜
レポートサマリー
「分散性」や「オープン性」といった従来のブロックチェーンの価値観から、「実用性」「規制適合性」「既存インフラとの接続性」など、社会実装に必要な要素へと重心が移りつつあり、それらを反映した新しいL1チェーンの開発が進んでいる。ステーブルコイン、RWA、デジタルIDといった複数の潮流が交わる中で、ブロックチェーンは単なる技術から「次世代の金融・経済インフラ」へと進化しつつある。
はじめに
L1チェーン(レイヤー1チェーン)とは、BitcoinやEthereumのような、ブロックチェーンの基盤となるレイヤーの技術を指す。固有のネットワークやコンセンサスアルゴリズムを持ち、トランザクションを直接記録・検証できるブロックチェーンである。また、このL1チェーンとは別にL2チェーンというものも存在する(Arbitrum、Optimism等)。L1チェーンは、ブロックチェーンの安全性と分散性を重視して設計されているため、スケーラビリティが課題であった。例えば、単位時間で処理できるトランザクション量の限界や、ネットワークが混雑するとガス代(手数料)が高騰し、一般ユーザーや小規模アプリケーションにとって利用しづらいところがあった。これらの問題を解決するために登場したのがL2チェーンであり、トランザクションの大部分をL1の外で処理し、最終的な結果だけをL1に記録する仕組みを採る。これにより、安全性はL1に依存しつつも、取引スピードの向上と手数料の低減が可能になり、ブロックチェーンのエコシステムがさまざまなユースケースに適用されることに貢献してきた。
新たなL1チェーンの開発
このような発展をたどってきたブロックチェーンのエコシステムであったが、近年新しいL1チェーンが金融サービスを持つ大手企業によって開発される動きが出てきている。次の表にそれらの会社名とチェーン/プロジェクト名、概要をまとめた。概要については、各チェーン/プロジェクトのトップページから抜粋・要約しており、必ずしも同じ観点からの比較とはならないが、各社が何を訴求しようとしているかがうかがえる。
| 会社名 | チェーン/プロジェクト名 | 概要 |
|---|---|---|
従来の金融機関が決済や資産のトークン化を行うために設計されたエンタープライズ指向の分散型台帳サービス。金融機関は独自のブロックチェーンを構築・運用せずに、セキュアかつコンプライアンス対応の取引基盤を利用できる。 |
||
Circle |
USDCをネイティブガスとし、即時ファイナリティ、プライバシー保護との両立、安定した取引手数料体系を備え、グローバル決済・FX・資本市場取引等におけるステーブルコインネイティブのユースケースへの最適化を目指す。 |
|
Stripe / Paradigm |
現実世界でのステーブルコインを用いた決済に適したものになっていない従来のブロックチェーンインフラの課題に対応し、トレードに専門化。AI系や銀行・コマースなどの名だたる会社(OpenAI、DoorDash、Deutsche Bank、NuBank、VISA等)から設計に関する助言を受けている。 |
ここから特徴的な点が見て取れる。いずれの取り組みも、以前から当シリーズでも取り上げてきたように、ステーブルコインの技術的な成熟・法規制の整備が進み、本格的な普及へと差し掛かってきたところで、インフラとして既存チェーンの課題に対応するものという点は共通している。また、そのために必要となる技術的な共通点も多くある。他方で、表から明らかなように、各チェーンでフォーカスする点が異なっており、各社の思惑等が見て取れる。以下、いくつか考察しよう。
共通するポイント
これらの新たなチェーンには、次のような共通する特徴がいくつか示されており、ステーブルコインや資産のトークン活用を最適化することを目指していることがうかがえる。なお、執筆時点(2025年10月初旬)ではいずれのプロダクトもまだ開発中ないし試験段階であり、公開されている設計目標等からまとめている。
-
プログラマビリティ単なる分散型台帳ではなく、スマートコントラクトを通じた支払いの自動化、資産トークンのロジック制御、決済ワークフローの組み込みを可能にする。ArcとTempoはEVM互換である一方で、GCULはPythonベースのスマートコントラクトであり、いずれも幅広い開発者の取り込みを狙っている。
-
ガス代や取引コストの予測可能性通常のブロックチェーンはガス価格が変動しやすく、企業利用にはコスト予測が難しい。これらのプロジェクトでは手数料支払いを容易なものにしたり(事実上のFIAT通貨建てや月額課金等)、透明・予測可能にする設計を採る。
-
確定性があり迅速なファイナリティ決済用途では「いつ取引が最終化されたとみなすか」が重要であり、サブ秒レベルでのファイナリティを目指す設計を志向している。また、複数アセット・通貨の交換を一連の操作でネット決済またはアトミック処理できるような設計を目指すことにも触れられている。
-
コンプライアンスいずれも設計思想において許可型のネットワークとなることを示しており、また自社の既存ケイパビリティ等を活用したKYC認証済みアカウントを前提とする構造となる可能性が高い。また、オンチェーンにおけるコンプライアンス・チェックポイントを設ける一方で、プライバシー考慮のためのオフチェーンにおけるKYC/アテステーションとの連携が考えられている。
-
パーミッション型のガバナンスBitcoinやEthereumなどのL1チェーンは、誰でもノードを立ち上げてネットワーク参加や検証に加わることができ、オープンなガバナンスが取られ、パーミッションレス型などといわれている。一方で、上記で取り上げた新たなL1チェーンは、いずれも企業やコンソーシアムが主体となってノード運用者やバリデーターをあらかじめ決めるパーミッションドの設計であり、ネットワークへの参加やコンセンサス形成はオープンには開放されていない。
なぜ今か?
いずれもステーブルコイン・RWA時代のインフラとして、既存インフラが抱える課題へ対応しつつ、各社がビジネスとしてこの機会をどう捉えているかが表れている。以下、論点ごとに既存の課題と、これらの新たなチェーンがどのように対応していくかをまとめる。
-
決済用の性能・ファイナリティ・安定したコストの保証既存のL1/L2チェーンは、パーミッションレス性や分散性を優先する分、ブロック確定まで時間がかかったり、混雑時にガス代が高騰したり、トランザクションの順序やファイナリティの一貫性が欠けるといった課題があった。企業・金融機関等が金融インフラとして日常業務で使うには、即時のファイナリティ・手数料の安定性・処理性能が求められる。
-
規制適合性・ID/KYCのチェーン層での実装従来のパブリックチェーンは、「誰でもアクセス可能」「匿名アドレスで取引可」という思想を持つ一方で、規制要件(AML/CFT、トラベルルール、KYC/KYB)との親和性が低いという構造的課題があった。これらはアプリケーション層で対処すると技術的にはバイパスの余地が残るため、トランザクション検証の段階でKYC済みアドレスのみを許可するといった仕組みが求められる。これら新たなチェーンは、MiCA※1が施行されている欧州でのEUDI Walletの本格導入、FATFによるトラベルルールのオンチェーン適用、米国でのGENIUS Act※2に続きデジタル資産市場での流通を規制するCLARITY Actを見据えた設計となっていることが考えられる。
-
大企業のアセットをレバレッジ従来のパブリックチェーンは強力な開発者エコシステムを築いてきた一方、大規模な商用顧客基盤・KYC済み利用者・銀行口座連携・流通網といった事業インフラは持っていなかった。いわゆるWeb2の大企業はこれらを保有しており、既存アセットをレバレッジすることで一気にユースケースのマス化を狙っているかもしれない。例えば、Google・Stripeは既存の加盟店やクラウド利用企業等との連携やKYC/KYB情報の活用、CircleはUSDCおよびその周辺のプロダクト群との連携が想定されている。
日本での動き
ここまでで述べたように海外で新たなL1チェーンが出てきている一方で、日本においても同様に新たなL1チェーンが構想・開発されてきている。代表的なものとして次の2つが挙げられる。
-
Japan Open Chain(JOC)日本企業が中心となって開発を進めているEthereum互換のL1チェーンであり、「誰でも利用できるパブリックなインフラ」を掲げている。Proof of Authority(PoA)を採用することで、高速なファイナリティと安定した低コスト決済を実現し、エンタープライズ用途に適した性能を持つ。規制対応面では、ブロックチェーンに記録されるデータの妥当性を検証するバリデーターへの厳格なKYC審査を行う体制を整えており、法令遵守やAML/CFTに配慮したネットワーク設計がなされている。大手企業がバリデーターとして参加し、既存の顧客基盤や事業資産との連携も視野に入れている。
-
Japan Smart Chain(JSC)日本国内の規制・制度環境に適合したブロックチェーンとして構想されているEthereum互換のL1チェーンである。全てのノードを日本国内に配置してデータ主権を確保し、またそれらは日本の大手企業の参加を前提に設計されており、オンチェーンでのKYC対応、ブラックリスト適用、低コストかつ高速な決済処理など、法令遵守と商用利用を前提にした機能をチェーン層に組み込む点が特徴と言える。興味深い点は、KYCの結果をプライバシーと両立させながらオンチェーン上で活用するためにDecentralized Identifier(DID)技術を用いているところだ。GCUL・Arc・Tempoなどのように、規制適合性をチェーン層で実装し、KYC等のバイパスの余地を無くす考え方は同じである。他方で、どこまでオンチェーンに情報を置くかというプライバシーとのバランスや、紐づけるIDを結局のところチェーン開発企業のID体系に依存するとなると、本当の意味での分散型プラットフォームとは言えなくなってしまうという課題があった。JSCの構想は、KYC済みのユーザーにDIDを発行し、そこからSoulbound Token(SBT)とVerifiable Credential(VC)を用いて、この両方の課題を解決しようとしている。例えば、とあるサービスをユーザーが利用する際に、スマートコントラクトがオンチェーンでSBTを確認することで「KYC済みユーザー」であることを判定し、必要に応じてVCの提示を求めてオフチェーンで必要な情報のみを確認することが可能になる。
まとめ
ステーブルコインが市民権を増す中、それらと既存金融の仕組みを橋渡しをするプロダクト(例えばUSDCの発行体であるCircleによるCircle Payments NetworkやCircle Gatewayなど)が出てくる一方で、金融の仕組みそのものを創り変え得るインフラと言えるブロックチェーンレイヤーの開発も進んできている。また、これまではクリプトテックとIDテックは、同じWeb3でくくられながらも少し異なるところで発展を遂げてきたが、オープン・分散型と規制対応・プライバシーのバランスを両立する解決策として、それらの交点が見えてきた。
これらは実際の決済や送金等で使われることや、その先にはキャピタルマーケットでも用いられることを見据えた社会実装の進化を示しているのではないだろうか。
※各技術の名称や仕様等は執筆時点(2025年10月初旬)のものであり、変更される可能性があります。
※本レポートに記載された会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
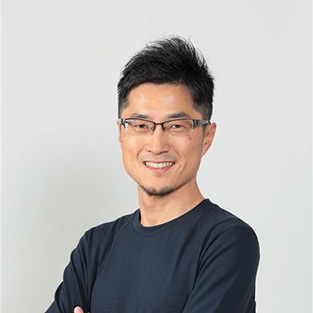
執筆者:公門 和也 Chief Growth Officer & Investment Partner, FINOLAB Inc.
電通総研(当時ISID)にてソフトウェア先端技術のR&Dと案件導入、黎明期からフィンテックの調査やFIBC(FINOPITCHの前身)の運営等に携わった後に渡米。サンフランシスコでは現法VPとしてスタートアップ出資と顧客企業とのオープンイノベーション事業の推進や、当地で新会社Dentsu Innovation Studioを設立し取締役COOを歴任。2025年より帰国し、FINOLAB参画・現職就任。
