RWAトークン化が示す社会インフラの次章
レポートサマリー
2024年から2025年にかけて、ステーブルコインを巡る議論と実装は、新たな段階へと進みつつある。2025年5月に開催された、米CoinDesk社主催の暗号資産・Web3に関するグローバルイベント「Consensus 2025」では、大手金融・テック各社の参入やステーブルコインの進化と多様化、そして(当時)米国議会で進む規制法案の行方が焦点となり、その背景にはRWA(Real World Assets)トークン化が金融および社会インフラとして重要な役割を担うことが見える。また、2025年8月18日にはJYPC社が金融庁から資金移動業として登録され、円建てステーブルコインを発行する準備が整った。本稿では、こうした潮流の中でステーブルコインが市民権を獲得する上での論点を整理し、日本市場での行方を考察する。
目次
ステーブルコインの社会実装
当レポートでは2025年5月に「ステーブルコインが変える決済の未来:日本の法整備・国際動向とスマートコントラクトがもたらす新たな可能性」を発表した。そこでは主要ステーブルコインの技術的アプローチの違いや状況、そしてスマートコントラクトを活用することで生まれる新たな可能性について紹介した。その後の数カ月間でも各社からさまざまな発表が出てきており、その社会実装の進み具合が見て取れる。
こうしたステーブルコインの動きをよく見ると、単なる通貨の代替手段としての側面だけでなく、RWAを裏付けとしたデジタルトークンの発行・取引のデジタル化によって、その仕組みが整備されつつある点が一つのポイントといえよう。例えば、2025年5月にトロントで開催された「Consensus 2025」では、こういった流れが技術・規制・実需の各視点から具体的に語られていた。
RWAとは
RWAとは、現実世界に存在する資産を指す言葉であり、具体的には不動産・債券・株式・コモディティ(商品)など、物理的または法的な裏付けを持つ金融資産や実物資産が含まれる。これまでこうした資産は、伝統的な金融システムの中で管理・取引されてきたが、そのプロセスには多くの仲介者と手続き、時間的・金銭的コストが伴っていた。
こうしたRWAをブロックチェーン上でトークン化する、つまりデジタルなトークンとして表現し、取引可能にするという試みは、従来の金融インフラを効率化・透明化し、流動性を高める動きとして近年注目を集めている。例えば、不動産物件の所有権を分割してトークン化すれば、従来よりも小口で投資・売買が可能になる。債券の利回りを担保にしたステーブルコインや、企業の売掛債権を裏付けにしたトークンなども出てきている。
このRWAのトークン化は、単なる技術的な話にとどまらない。その本質は、信頼性のある価値の裏付けを持つデジタル資産となり、金融インフラの可能性を拡張する点にある。RWAトークンは、それ自体が金融取引の新たな対象となるのみならず、安定的な担保資産としても機能し得る。そしてそれは、分散型金融(DeFi)と中央集権型金融(CeFi)をつなぐ架け橋としての役割も担いつつある。
Consensusとは
Consensusは、暗号資産・Web3にフォーカスした世界最大級のカンファレンス。ブロックチェーン・暗号資産はもちろんのこと、近年であればAIとの組み合わせやその周辺技術など、テーマが拡大してきている。暗号資産メディアのCoinDesk社が主催し、業界の起業家・開発者・投資家・政策立案者が一堂に会する場として、2015年から毎年開催されているイベントである。
同イベントは、コロナのさなかに米国ニューヨークからテキサス州オースティンに場所を移して2022年〜2024年にも開催されてきたが、2025年は2月に香港、そして5月にカナダ・トロントにて行われた。2026年は2月に香港、5月に米国マイアミにて開催されることがアナウンスされている。
【Consensus 2025開催概要】
- 開催期間:
-
2025/5/14~2025/5/16
- 開催場所:
-
カナダ トロント メトロ・トロント・コンベンションセンター
- 来場者数:
-
14,771名(102カ国から来場)
- 主催:
-
CoinDesk

ステーブルコインを巡る動き
筆者自身の実感や他の参加者の声によると、今回のカンファレンスではステーブルコインに関するテーマが最も多く語られていた印象がある。実際にステーブルコインに関連するセッションやプロダクト展示が目立ち、業界全体の注目度の高さが感じられた。特に今回は、その社会実装フェーズが一段階進み、大手プレイヤーの参画を伴う現実的な活用と制度設計の両面で新たな展開が見られた。
「Consensus 2025」を前にした1〜2ケ月間は、大手フィンテック企業や決済事業者による相次ぐ発表が注目を集めてきたので、これらを取り上げた話題が多かった。下表の通り大手各社の、既存の強みを生かしつつ、ステーブルコインやWeb3といった新興技術を取り入れる動きが加速している。中でも、SWIFT(国際銀行間通信協会)をバイパスした国際送金や、ステーブルコイン残高を活用したカード決済など、「従来の金融インフラ×分散型テクノロジー」の融合が進んでいる。
25/4/1 |
CircleがNYSEへの上場申請 |
25/4/21 |
Circleが大手銀行とCircle Payments Networkを発表 |
25/4/23 |
PayPalがPYUSDに年率3.7%の利回りをPayPalまたはVenmoの残高に付与を発表 |
25/4/28 |
Mastercardがステーブルコイン残高からのカード決済に対応 |
25/4/30 |
VISAがステーブルコイン残高からのカード決済に対応 |
25/5/2 |
MoneyGramが170カ国以上で仮想通貨からの現金の出金に対応 |
25/5/6 |
VISAがBVNKと資本業務提携 |
25/5/6 |
CoinbaseがAPI/AIエージェント向け決済プロトコル「x402」を提案 |
25/5/7 |
Stripeが101カ国対応のステーブルコイン金融口座とUSDBのサポートを発表 |
25/5/13 |
RobinhoodがカナダのWonderFi(暗号資産関連事業を展開)を買収を発表 |
(電通総研調べ)
これらの内容だけでも、ステーブルコインを含むデジタル通貨の社会実装がすぐそこまで来ていることが想像できる。例えば、上述のプレイヤーおよび発表内容のみでも、理論上はデジタル通貨で経済活動が完結することとなる。
-
給与払い:BVNKのデジタル通貨対応のGlobal Payrollを用いた支払い
-
国際送金:CircleやStripeが発表したSWIFTを使わない送金
-
現金引き出し:MoneyGramを用いたデジタル通貨の各所現地通貨での引き出し
-
支払い:デジタル通貨口座からのVISA・Mastercard等でのカード決済
さまざまなデジタル通貨がある中で、FIATにペッグされ価格が安定しており流動性もあるステーブルコインは、多くのユースケースに用いられる選択肢となることであろう。
ステーブルコインの進化と勢力争い
日本/日本円で生活していると実感は湧かないかもしれないが、例えばドルでは「Consensus 2025」開催時点(2025年5月)において、一般消費者が購入できる金融資産には年率4%程の金利がリスクフリーで付く。従来のステーブルコインはFIATにペッグされたトークンであるのみで、金利が付くということはなかったが、過去2年で金利付きステーブルコインの市場規模は69倍に成長したと言われる(それでも2025年5月時点でのステーブルコイン全体$230Bに対して$7Bで3%)。
ステーブルコインの主な収益源は、裏付け資産の運用益によるために、プレイヤーにはより多くの資産を持つ動機が働く。既存の大手勢力であるUSDTやUSDCは金利がない一方で、金利のあるものを出せば利用者に新たなメリットを訴求できる。後発組にとっては機会と考えられていたり、はたまた金利付きステーブルコインは役割の異なるものであるという議論もある。従来型・利回り型それぞれの性質と利用シーンを整理すると以下のようになる。
-
従来型:金利なし。決済レールとしての即時性と流動性が目的。
-
利回り型:MMFなどに匹敵する利回りの上、モビリティもある。担保としてとどめておく価値が高い。
規制の動き
「Consensus 2025」で多くの関心を集めていたことは、米国議会で審議中(当時)のステーブルコイン法制GENIUS Act・STABLE Actについてであった。そのような中で、現米国大統領の子息でAmerican Bitcoinの共同創業者・最高戦略責任者であるEric Trump氏や、米政権でデジタルアセット分野の諮問委員会事務局長を務める(当時)Robert Hines氏が登壇したこともあり、多くの話題と聴衆を集めていた。これらの法整備における論点の中心は以下2点にあった。
-
金利付きステーブルコインの規制分類「証券」として規制対象とするのか、従来型(決済用)ステーブルコインのように「非証券」として扱うのかが、各社の戦略設計に大きな影響を与える。
-
発行主体の所在要件米国拠点の発行者のみが決済用ステーブルコインを発行できるとされる可能性があり、外国企業となったTether(USDT発行主体)への影響は大きいと見られている。
なお、GENIUS Actはその後、2025年6月17日に上院で可決・同年7月17日に下院でも可決され、その翌日にはトランプ大統領によって署名され、正式に法律として成立することになった。
RWAトークン化の波
技術革新に加え、このような大手プレイヤーの動きと地政学的動向が交錯する状況ではあるが、本質的に進んでいることはRWAトークン化ではなかろうか。金利付きステーブルコインなどさまざまなものが出てきているのも、米短期国債(T-Bill)等のRWAがオンチェーンで扱いやすい形にトークン化された結果であり、その成熟度合いは注目に値する。
例えば、世界最大の資産運用会社であるBlackRockが、2024年3月にBUIDL(BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund)をローンチし、2025年5月時点で総運用資産残高は$2.9Bに達している。BUIDLはEthereum 上のERC-20 トークンで、T-Bill・リバースレポ・現金同等物等で運用され、得られた利息は日次で自動的に再投資される。トークンとしての高いモビリティを生かし、ステーブルコインの担保等に活用されており、24 時間 365 日の即時決済・業務効率の向上・透明性の強化といったメリットが期待されている。Securitizeがこのトークン化の技術的基盤を支えており、発行主体はBlackRockだが、トークンの発行・管理はSecuritizeのプラットフォーム上で行われ、投資家は同社でKYC/AML手続きを完了した後にトークンを受領する。Consensus 2025 Torontoには他にChainlinkやBitGoなども参加しており、RWAトークン化を支えるエコシステムが着々と形成されつつあることがうかがえた。
今後注目すべき論点:リアルユースケースと需給バランス
ドル建てステーブルコインの多くは実際に使われることを見据えた動きに入りつつあるといえるだろう。需要サイドから見ていくと、輸出入や越境EC・フリーランス報酬など、国境をまたぐ取引ではドルの実需は大きい。ステーブルコインとして24時間365日決済の即時性が可能になることで、特にデジタル空間においてはよりスムーズな取引を実現することが予想される。一方で、供給サイドでもリスク管理インフラが整備され始めている。2025年6月、Coinbaseは米CFTCの認可を得たクリプトのデリバティブである無期限先物を米国内で提供すると発表。それは24時間ヘッジが可能になることを示している。スマートコントラクトを用いることで、実行のメカニズムをプログラムに入れることができ、在庫や為替リスクを自動ヘッジしやすくなるのは確かであろう。ただし、こうしたデリバティブ等の金融取引を支えるには十分な取引量が不可欠で、このマーケットを受け入れるプレイヤーを増やすことが当面の課題といえる。
日本におけるステーブルコイン市場の行方
日本では2022年にステーブルコイン関連の法制度が整備され、2025年に入りさらなる管理・運用要件の一部緩和に向けた検討や、電子決済手段等取引業者の国内初の認可事例が出るなど、法規制に対応したステーブルコインの実利用が動き始めた。また、2025年8月18日にはJYPC社が金融庁から資金移動業として登録され、同年秋に円建てステーブルコインを発行する見込みとなった。今後においては、ドル建てステーブルコインの課題と同様に、クロスボーダー貿易や取引など市場規模が大きく必要性の高い領域で流動性をつくり、その後国内の各種ユースケースを普及させていくことが現実的なところではなかろうか。
また、米政権で暗号資産政策を統括するDavid Sacks氏が法案審議中(当時)に「GENIUS Actが成立すればステーブルコイン経由で数兆ドル規模の資金が米国債に流入し得る」と指摘したように、円建てステーブルコインも日本国債の新たな買い手になり得るかが注目される。制度面では日本が米国に先駆けてステーブルコインに関する電子決済手段規制を整えた一方、金利水準・国際決済での取引ボリューム・裁定取引を支える流動性の厚みでは依然ドルに後れを取っており、現時点で同規模の需要喚起は難しいかもしれない。しかし今後、日銀の金融政策転換やASEAN・北米向け貿易、訪日消費、オンチェーン資本市場の拡大といった越境ユースケースが拡がればその可能性は変わる可能性がある。
さいごに
ステーブルコインをめぐる最近の動きの本質は、RWA トークン化を起点とした金融インフラの進化にあると思われる。大手プレイヤーは既存の顧客基盤と流通チャネルを武器に、新興技術を取り込みながら付加価値を創出している。これらの仕組みが真の社会インフラとして定着するかどうかは、どの国で・どのユースケースが最初の突破口となり、市場を拡大させるかによっている。今後の国内における発行主体の認可取得と実際の流通、そしてスケールする具体的ユースケースがどこで生まれるかを注視したい。
※本レポートに記載された会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
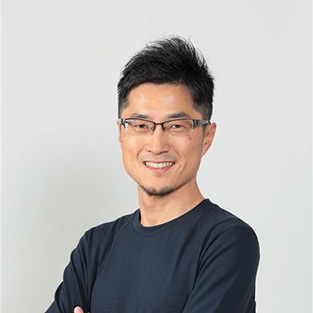
執筆者:公門 和也 Chief Growth Officer & Investment Partner, FINOLAB Inc.
電通総研(当時ISID)にてソフトウェア先端技術のR&Dと案件導入、黎明期からフィンテックの調査やFIBC(FINOPITCHの前身)の運営等に携わった後に渡米。サンフランシスコでは現法VPとしてスタートアップ出資と顧客企業とのオープンイノベーション事業の推進や、当地で新会社Dentsu Innovation Studioを設立し取締役COOを歴任。2025年より帰国し、FINOLAB参画・現職就任。
