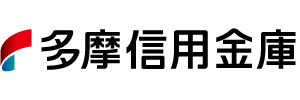多摩信用金庫が0から始めるデジタルマーケティングを支援、活用拡大への道筋をつくる
- 金融業務
- 顧客接点改革
- 業務・プロセス改革

2023年に創立90周年を迎えた「多摩信用金庫」。「有限責任立川信用組合」を前身とし、東京都23区外の多摩地域を中心に、“地域の課題解決インフラ”として預金・融資・資産運用など幅広いサービスを提供し、地元企業や地域に住まう人々の発展を支援しています。出張所含め81カ所に上る店舗のネットワークと対面による丁寧な対応で、長年、住民の小さな困りごとにも寄り添った事業を展開してきました。
一方で、共働き世帯の増加やコロナ禍後の対面営業を取り巻く状況の変化を背景に、非対面のコミュニケーションチャネルの確立にも乗り出します。2024年には、その足がかりとしてMAツールの導入と、SMSやメールを活用した情報発信に関するPoCを実施、デジタルマーケティングの基盤を築きました。同金庫にとって新たなチャレンジとなったこのプロジェクトをデジタルマーケティングコンサルとしてサポートしたのが電通総研です。
プロジェクトの主幹部署となった、価値創造事業部 課題解決企画グループ 主任調査役の臼井浩樹氏は「何から始めたら良いかもわからないという当金庫の状況を丁寧に汲み取り、KPIの定め方から、ツール選定のサポート、施策結果の分析の仕方まで、納得感のある提案をもらいました。初の取り組みをスムーズに進められたのは電通総研の伴走のおかげです。今後は配信する情報のジャンル拡大など、デジタルマーケティングの業務領域を広げていくとともに、紙ベースのお知らせが主となっている営業店との連携等の取組みを進めたいと考えています」と評価し、笑顔で今後を見据えました。
目次
「このままでは取り残される」
対面の機会が減る中で覚えた危機感と、非対面チャネルの必要性
非対面チャネルを活用できれば、サポートを必要とされているお客さまが自ら情報をキャッチして動いてくださる。対面以外の接点をいち早く展開し、いかにして会えないお客さまに対してもタッチポイント増やしていけるかが重要だと考えていました
価値創造事業部 課題解決企画グループ 主任調査役 臼井浩樹氏

長年地元の事業者等と共に地域の活性化・持続成長に努めてきた多摩信用金庫では、これまで個人のお客さまに対しても、密着型の対応で困りごとの解決に尽力してきました。「他金庫や地方銀行と比べても渉外担当者の人数が多く、ご相談の手段は基本的に訪問やご来店でした」と振り返る臼井氏は、その中で課題感も覚えていたといいます。
「共働き世代の増加に加え、コロナ禍を経て対面対応への不安感が高まるなど、お客さまにお会いしにくい状況が続いていました。対面による接点が持てないのであれば、非対面のチャネルを確立する必要があるのではないか。早めに新たな手段を講じられなくては、取り残されてしまう感覚があったのです」(臼井氏)。
“フットワークの軽さ”と金融業界の実情を踏まえた提案が、電通総研選定の決め手
電通総研は困っているときに相談をしたら、内容がまだ曖昧な段階でもすぐにレスポンスをくれました。一緒に仕事をするうえではそうした対応の素早さや信頼感も重要だと感じています
システム統括部 主任調査役 秋田宏介氏

多摩信用金庫では、当初そうした課題感を別のベンダーに相談し、非対面チャネルの必要性やビジョンの整理を行いました。しかし、その先の実行フェーズにおいて新たな課題が発生します。金庫として初の試みであったこともあり、「具体的な業務内容の整理や工程の具体化」「それを実行するためのツール選定」「KPIの設定や本格稼働に向けた必要な道筋の整理」といった詳細な推進方法のイメージがつかなかったことです。
「最初に相談したベンダーは、ビジョン整理などの学術的な分析をしっかりしてくれました。一方で、もらった分析結果から具体的に実行していく工程をくみ取るのは困難だった。次の段階に進む上では、そうした分野の知見に長けたところにサポートをお願いした方が、即効性があると考えたのです」と、臼井氏は新たなパートナー探しに至った理由を説明します。
こうした状況の中、電通総研がパートナーに選定されたきっかけは“フットワークの軽さ”だったと臼井氏。他案件の打ち合わせ時に本プロジェクトの支援について相談したところ、「すぐに提案書をまとめて、リモートのミーティングで支援可能な範囲などの具体的な話をしてくれた」とその迅速な対応を評価します。
臼井氏同様、プロジェクトに主幹として携わり、現在はシステム統括部の主任調査役を務める秋田宏介氏も「当時金庫内では、組織編成も含めた大枠のスケジュールが決まっていました。逆算するとすぐ実行フェーズに着手しなくてはならない状況だったので、とても助かりました」と同意します。
段階別のツール導入プランによって「現状」と「課題」が整理され、納得感ある選択ができた
難易度や予算を段階的に分けて複数の導入プランを示してくれたので、導入時の具体的なメリット・デメリットを想定できました。おかげで納得感をもってツールの選定とPoCを進められたと思います
経営戦略室 DX Lab 調査役 髙木皓平氏

実際の取り組みにおいては、ヒアリングシートで金庫の課題とプロジェクトにおける要望を細かく聞き取り、「ツール選定とシステムのグランドデザイン」「コンテンツ制作」「PoC結果分析」などの工程を一つずつ丁寧にサポート。基礎的な考え方や指標なども含めて、電通総研から納得感のある説明と進め方の提案があったといいます。
臼井氏と同じグループで共に本プロジェクトを主導した今西雄哉氏は、「大手の地方銀行やネットバンクで実施されている先進的な施策と、その上で描かれる“憧れの未来”を語ってくれるベンダーはたくさんいます。われわれも理想を思い描くことはできるのですが、そこに至るために具体的に何からどう始めたらいいのか、道筋を立てて進めていくのが難しいと感じていました。電通総研は、0からのスタートとなるわれわれと目線を合わせ、現状に沿った具体的な提案をくれました」と、提案の実現性を評価します。
MAツールの選定とシステムのグランドデザインにおいては、導入時に解決すべき金庫内の課題も踏まえたうえで複数の段階別プランを提示し、多摩信用金庫が選択できる方式に。その結果、実現におけるリソース・資金の確保やスケジュール上の課題等をあらためて整理し、着手可能な領域をしっかり選定できたといいます。
経営戦略室「DX Lab」に所属し、データ活用推進の観点から同プロジェクトに携わった髙木皓平氏は、「電通総研からは、実現可能なところから導入していくという考え方の基、金融機関での導入実績があるツールをメインに提案してもらえてありがたかったです」と語ります。電通総研からの提案に加え金庫が情報収集したツールについても同社がレビューを行ったうえで、総合的な判断として現状に一番適したMAツールであると「b→dash」の導入を決定しました。
b→dashの導入は多摩信用金庫が自身で実施することにしたものの、開発ベンダーとの打ち合わせには電通総研の担当者も同席。情報の蓄積方法やデータ連携の仕方など、システム面の細かな懸念点について踏み込んだ質問を投げかけ、実運用に向けたサポートが行われました。
「電通総研が率先して発言してくれた内容が、現在の運用にとても生きていると感じています」と髙木氏。また、臼井氏も「ツールの動きや設定に関しては、金庫の者だけですと知見や経験が足りず、踏み込んだ質問を投げかけにくい。機能上などの理由で『難しい』といわれた要望に対しても、専門知識のある第三者の立場から、改善案を含んだ意見をすぐ出してもらえたことで、視野が広がりました」とそのメリットを明かします。
「アジャイルマーケティング」スタイルのPoCで、有効な分析手法や進め方の確実な把握が可能に
PoCを伴走してもらったことで、1度目の振り返りと分析をしっかりしてから2度目に進められました。その結果、業務の流れとポイントがしっかり把握でき、より有効なPoCが実現できました
価値創造事業部 課題解決企画グループ調査役 奥住和也氏

導入後は、SMSやメールで個人向けの「消費性ローン」に関する案内を送付するPoCを実施。
価値創造事業部 課題解決企画グループ調査役の奥住和也氏は、配信するコンテンツ制作中の電通総研の対応について、次のように振り返りました。「自分たちでコンテンツを制作するのはメンバー全員が初めてでした。作成したものは電通総研にも共有して内容をチェックしてもらい、状況に応じたコンテンツの見せ方や内容自体の精査、インパクトのあるタイトルの付け方など、これまで私が考えたことのない観点から内容を軌道修正してもらえました」。
システム面に留まらない総合的なサポートについては、今西氏も賞賛。「当金庫のデジタルチャネルはもともと公式のHPしかなく、お客さまに届けたい情報を全て載せていました。PoC用のコンテンツを作成するときも同じように様々な情報を詰め込むような造りになっていたのですが、それでは情報量が多すぎると指摘がありました。例えば、1通目は短めのテキストでもテーマが気になった人はリンクを開いてくれる。アクションがなかった人には、2通目で追加の情報を見せるといった他の施策でも活用できる知見をもらえて、ハッとしましたね」
PoCは1回発信して終わりとするのではなく、効果検証を経て2回目を行う「アジャイルマーケティング」スタイルで実施。秋田氏は「当金庫の担当者だけでは、1度目の実施結果をしっかり集計・分析することは難しかったと思います。どのような集計方法で分析すれば、施策の有効度を図れる数値を見いだせるのか。電通総研にそこまで伴走してもらえたことで、今後の非対面マーケティングの方向性と方法を具体的に固めることができました」と、その意義を語ります。
KPIやクリック率など“判断の基準”を確立。既存施策との連携を広げるためにも、引き続きの支援に期待したい
ツールの活用方法に留まらず、PoCの施策状況全体を見て1つ1つ課題をピックアップして対応策を提案してもらえた。電通総研に支援をお願いして良かったと感じています
価値創造事業部 課題解決企画グループ 主任調査役 今西雄哉氏

PoC施策が実際の契約につながったかを正確に測ることは難しいものの、「直近半年では総契約数の内1割程度が、非対面チャネルで配信を実施したお客さまでした。配信対象のお客さまがメールやSMSを閲覧し、その後のHP遷移等のWEB行動に繋がったことを思うと、一定の効果が感じられます。メール開封率およびSMS上のクリック率も実施前の想定より高水準で、発信した情報を地域のお客さまがキャッチし、リアクションしてくれた実感があります」と臼井氏。
また、髙木氏はリアクション率について、「正直これまで数値を評価するための物差しを全く持っていない状態でした。電通総研からはセグメントごとの反応が良い施策や、メール・SMSが見られやすい時間帯など、他社事例も含めた丁寧なフィードバックがあった。数値の見方に加え、判断のめやすをもらえて助かりました」と思い返します。
今西氏はPoCの進行方法自体を次のように評価します。「2度目の施策スタート時には、われわれがどの程度ツールへの理解を深めているか、クリエイティブ制作への順応度なども見た上で、スケジュールを組んでくれた。その結果、2度目は少しタイトな進行でも滞りなく進められることを実感できました」
「当金庫はKGIを描くのが得意な一方、KPIに落とし込むのは苦手な傾向にあります」。臼井氏は金庫の課題をそう分析します。「この点についても、われわれの目線に合った形で一般的なKPI設定の仕方なども教えてくれて、金庫側の要望と組み合わせた設定方法を検討してもらえました。こちらの実情に寄り添った支援とアドバイスは、今後の施策を進めるうえでも大きなメリットになっています」
髙木氏は今後の展開として、既存施策との連携を視野に入れています。「金庫では、『多摩信用金庫アプリ』という独自サービスを提供しています。このアプリと連携し、アクセスいただいたお客さまの行動情報を今回のような施策に活かせるようにしていきたい」
同じDX Labでデジタルマーケティング運用に携わる原由樹氏も「さまざまな情報を取得・連携するとともに、生成AIなどの新しい技術も活用し、より効率的かつ魅力的なコンテンツ作成にも取り組んでいきたいと考えています」と意欲を語ります。
今回の取り組みは店舗の営業活動にも展開できると思います。さらに新しい技術も取り入れ、より効率的で魅力的な施策につなげていきたいです
経営戦略室 DX Lab 調査役 原由樹氏

臼井氏もデータの連携と施策への反映に意欲を見せます。「金庫内のシステムに保管されているお客さま情報とMAツールを連携させ、メール開封率の年代別分析などをさらに詳細に行って必要な方に必要な情報を的確に届けていく取り組みも進められたらと思っています。また1からの取り組みになりますので、電通総研には引き続き同様の支援をお願いできるとうれしいです」
-
※記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
-
※記載情報は取材時(2025年6月)におけるものであり、閲覧される時点で変更されている可能性があります。予めご了承ください。