クロストーク

新人の新人による新人のための研修へリニューアル!
朝会改善プロジェクトの裏側に迫る
ISIDでは、例年、新卒入社後3ヵ月間の基礎研修が終わると、各事業部に配属。さらに技術職はそこから3ヵ月間のIT研修を経て、各部に本配属されます。
各事業部ではIT研修の期間中、「朝会」と呼ばれるミーティングを実施。新入社員に「事業部内の各部がどのような仕事をしているのか」を知ってもらうために、先輩社員から各部の紹介を行います。
2019年に入社した矢野圭祐も、そんな朝会に参加した一人。「私たちの事業部では若手社員が朝会をリードし、新入社員が一日でも早く事業部になじめるようサポートするのが慣例です。だからこそ、新入社員の頃から、先輩たちのどんな話が役立ったのか、逆にどんなことを知れるとよかったのか、その想いや課題をコツコツとためていました」
そして、2年目に入る直前、同期とともに「朝会改善プロジェクト」を発足。新入社員一人ひとりに寄り添い、成長にドライブをかけるためには何をしたらいいのか——プロジェクトを推進した矢野圭祐とリニューアル後の朝会に参加した四百目拓磨に話を聞きました。
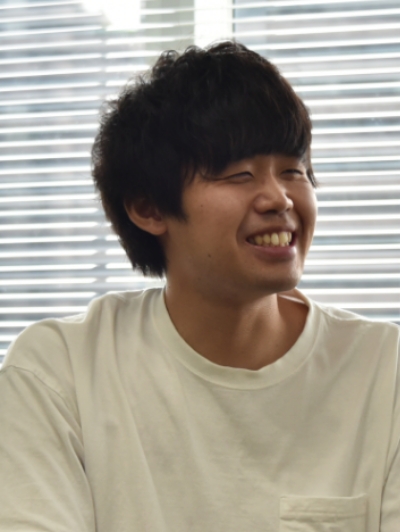
四百目拓磨
コミュニケーションIT事業部
入社2年目

矢野圭祐
コミュニケーションIT事業部
入社3年目
新入社員自ら新入社員研修の課題解決に動き出す
「朝会改善プロジェクト」の立ち上げに至った経緯を教えてください。
矢野
私が所属しているコミュニケーションIT事業部(以下CIT事業部)の朝会は、部長・中堅社員・若手の3人1組で行っていました。それぞれの立場から話を聞けることや、社内人脈ができる点では非常に有益だったものの、人によって「業務」「一日の働き方」「これまでの経験の失敗談」「お客様のこと」など、話の粒度がバラバラで、事業部への理解を深める材料としては過不足がありました。
また、実際10月から本配属されてOJTが始まったときに、業務に忙しい先輩方を見ながら「これを共通知識として事前に教えてもらえればもっと役に立てたのではないか」と歯がゆく感じたこともあったんです。このような経験から「来年、自分が2年目として後輩に教える立場になるのであれば、新入社員の皆さんには同じ思いをせず前に進んでほしい」という思いが日に日に強くなっていったんです。
「朝会」リニューアルのポイントは?
どのようにプロジェクトを進めたのですか。
矢野
最初は、受講側である同期と運営側である先輩に話を聞いて、朝会に対して感じている課題を整理しました。当時CIT事業部では組織を活性化するためのワーキンググループが立ち上がっており、まずは整理した課題をそのワーキンググループのリーダーであるCIT事業部長補佐に持っていきました。そしたら「やりたいなら、やってみなよ。」と。当時新入社員の私からすると約300人を束ねる事業部長補佐の立場の人が、こんなにも真剣に話を聞いてくれて「いいじゃん!いいじゃん!」と言ってくれて、自分の仕事のキャッチアップでも手一杯だったのですが、やるしかないなと思いましたね。多くの同期が協力してくれてすぐに動き出すことになったんです。
四百目
私はそのときはまだ学生だったので、この話は後になって聞いたのですが、それだけの上司や先輩社員が動いてくれたことが純粋に嬉しかったですね。
矢野
この時点ですでに3月。新入社員が入ってくるまでは残り3ヵ月というところでした。改めて“朝会”の目的を明確にするところから着手しました。私自身が感じていた課題から「新入社員が事業部への理解を深める」「業務に必要な最低限の知識をつける」はもちろんのこと、「新入社員の不安を払しょくする」「先輩たちの新入社員への理解を深める」も追加しました。
四百目
私たちはいわゆる「コロナ世代」。新型コロナウイルスの感染が拡大し、研修もリモートで受けてきました。この朝会がなかったら今でも「隣の部署が何をしているかわからない」「部のメンバー以外誰も知り合いがいない」という状況に陥っていたかもしれません。しかし、「先輩たちの新入社員への理解を深める」という目的のもと、私たちの日報を事業部全体に公開してもらったり、部長陣とのオンライン交流会が実施されたおかげで、リモート環境下でも気軽に声をかけてくれる先輩たちがいて、何か不安に感じたときに相談できる人もいます。実際に配属直後に出社した際に、矢野さんにも社内便の出し方を教えてもらいました。
矢野
そんなこともあったね(笑)。私自身、研修時と配属後でコピー機の使い方が違って困ったことがあったので、些細なことでも何でも聞いてねと伝えるようにしていました。
今の2年目のメンバーは私たちの新入社員の時代以上に、不安を抱えていると思います。オフィスにいればランチにも行ける、頑張ってる?と声をかけることもできる、でも今はそれができない状況です。その中で“朝会”の果たすべき役割は知識を得る以上の意味があると考え、そのような目的も加えました。

一方で、共通知識の習得はどのようなことを実施したのでしょうか。
矢野
CIT事業部のどの部署に配属されても必要となるような「インフラ技術」と「顧客の業務」の講義を行いました。IT知識は人によって様々です。IT研修を経て開発のノウハウやスキルは身についているものの、ネットワークやサーバの知識は事業部によって要否が異なるためOJTで教わる部分が多かったんです。しかし、CIT事業部では、触れることも多いため、事前に最低限の知識は講義形式で学ぶようにしました。
四百目
このインフラ技術講義で教えてもらったクラウドの内容は、非常に役に立ちましたね。配属後にアサインされたプロジェクトが、インフラ基盤をオンプレミスからクラウドに移行するプロジェクトだったので、クラウドの概念や、オンプレミスとクラウドのメリット・デメリットなど、この講義のおかげで案件のキャッチアップがとてもスムーズでした。
矢野
これらの内容は、新人だけでなく、部署異動してきた方にも役立つものになっているので、講義の資料や録画は事業部内で共有して、いつでも見られるようにしています。
四百目
そのときすぐに理解できなくても、見返せますし、案件が変わってその知識が必要になったときに再度確認できるところもいいですね。
「教わる」から「教える」まで、新人が成長する礎に
今回のプロジェクトについて、周りからどんな反響がありましたか?
矢野
昨年はコロナ禍で対面研修も難しく、例年通りには新人を受け入れられない状況だったのですが、「資料も含めて新人の受け入れ準備が整っていたおかげで、どうにか乗り切ることができたよ」と言ってもらえました。
ただ、それ以上に2年目の皆さんがすごく声をかけてくれて、他の事業部の同期にも講義を受けてもらいたいくらいですと言ってもらえたことはとても嬉しかったです。
四百目
あれ以来、先輩方とは仲良くしてもらっていて、出社した際にはよく一緒にランチに行っています。また、CIT事業部ではコロナ禍でのコミュニケーションを促進するために、2021年6月に第1回e-sports大会が開催されました。ゲームソフトは大乱闘スマッシュブラザーズで、他の年次の先輩とペアになって、事業部長と戦うなど大いに盛り上がりました。普段の業務では関わりがない先輩とも交流ができて、とても楽しかったです。事業部長は決勝で負けてしまったので、第2回の開催をすでに意気込んでいます(笑)。
今後、この研修をどう発展させていきたいですか?
矢野
この研修は、2〜3年目が担当しているのが一番のポイントです。教わる立場と教える立場の両方を経験できる。インプットからアウトプットまで経験して成長できるプロジェクトになっているので、これからも継続して新人の成長を支援できるプロジェクトになればと考えています。実際に今四百目さんには朝会や事業部への新人紹介をリードしてもらっています。期待していますよ!
四百目
ありがとうございます、プレッシャーですね(笑)。
新しくなった朝会は、恐らくCIT事業部の伝統になると思います。今の3年目の先輩たちが作りだしてくれたものを、リモートが当たり前となった今、さらに発展させながら次の世代につなげていきたいと思います。


